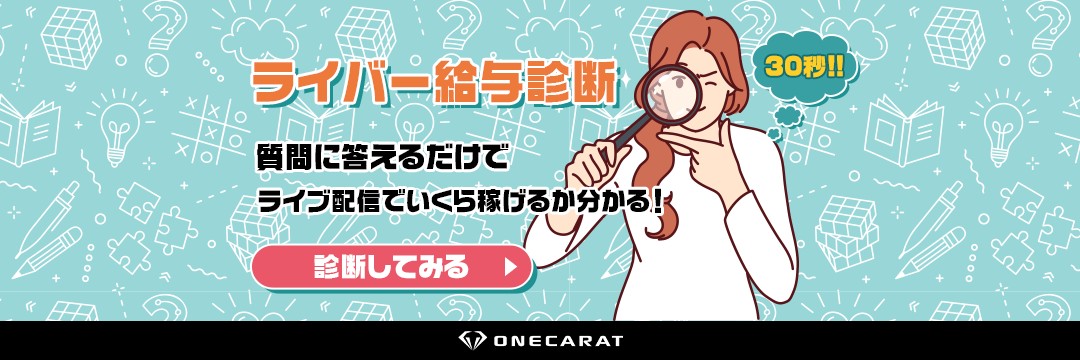
30秒で診断!ライバー給与診断!
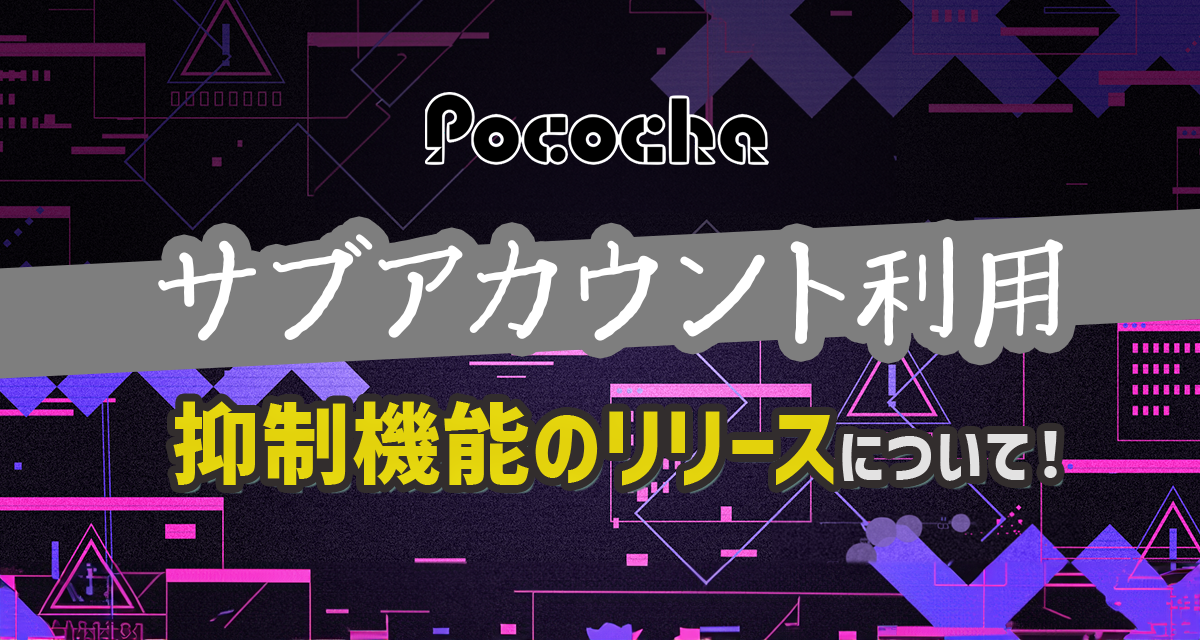
Pocochaはサブアカウントの利用は厳禁!
Pocochaでは、サブアカウントを禁止し取り締まりの強化をしています。
その中で6月には『同一人物が複数のアカウントを用いて一人のライバーを応援する行為を抑制する機能』もリリースされました。
今回はその機能にさらに抑制機能が追加されましたので、その機能について解説していきます。

目次
\今月のおすすめ!/
▲から無料でインストールできます▲
『通常の起動以外の方法で、アプリを起動させる行為』の抑制
こちらは不正なアカウント利用を目的とした新たな機能です。
判断基準は従来からの基準のまま、より不正の検知の範囲を広げるものになります。
不正対策の調査はAIなどを検知に用いていますが、ペナルティーや最終確認を実行する際には、運営側の部署が人口で対応し判断しますのでAIのみの動作で判断されることはありません。
※後日強制アップデートも予定されております。
※アプリバージョンは5.19.2 より内蔵された機能です。
Pocochaでは規約・ルールブックに違反しないご利用の中で盛り上がることで生まれる、
配信枠同士の健全な環境を作っって行くことが重要になっています。
たくさんのサブアカウントによる応援は、Pocochaが目指している健全な競争環境を阻害することにつながるため、昨年から継続的なサブアカウント取締り強化を実施しております。
10人のリスナーさんが応援しているライバーさんと、
1人のリスナーさんが10個のサブアカウントで応援しているライバーさんの配信枠が同じ盛り上がりと評価される環境は、フェアな競争環境ではありません。
そのため、取締り強化を実施していくことで、ルールを守って活動している配信枠に正当に光が当たる状態を作っていきます。
具体的には、今回のような「同一人物が複数のアカウントを用いて一人のライバーさんを応援する行為」の抑制機能の開発や、サブアカウントを通した応援による応援ポイントへの影響を少なくするなどの根本対応を実施していく予定です。
複数アカウントの利用に関して、「不正行為(複数アカウント、bot利用など)」の通報カテゴリーに通報いただくことで、対応実施につながります。
可能な限り全ての通報に対して確認を行いますが、審査人員の都合上時間がかかる可能性があります。
※「お問い合わせ」からの通報は確認できないため『通報機能』を使用してください。
ご協力お願いいたします。
サブアカウントの判定ロジックの詳細を公開することで、その基準から逃れる行為を実現しやすくなってしまいます。
例えば、「サブアカウントは10個以上所有したところから判定基準に入ります」などと伝えた場合、「9個まででサブアカウントの作成を留めて違反行為をする」などが容易になってしまいます。
そのため、厳密な審査基準などは公開しておりません。

[Q1]通報した相手がすぐに機能制限にならないのはなぜ?
[Q2]何も違反していないのにユーザーが利用制限受けているのはなぜ?
配信を続けていると、自分で判断ができない悩みや例外が出てきます。
ライブ配信の悩みを相談できる人がいないときは、ライバー事務所を活用してはいかがでしょうか。
一人で深く悩み過ぎて時間を浪費せず、事務所を利用してプライベート時間をしっかりと確保しましょう!

この記事で紹介したことをまとめました。
空いた時間で配信するからこそ、メリハリをつけた活動をしましょう。

ライブ配信の最新情報を常に獲得するには、事務所所属のライバーとして活動するのも一つの方法です。
事務所所属のライバーとして活動をする主なメリットは以下の4つ。

Pocochaの最新情報を常に獲得するには、事務所所属のライバーとして活動するのも一つの方法です。
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
他にも、フリーライバーと比較すると事務所で受けられるメリットの方が多くなることが大半です!
ライブ配信に興味がある方は、
ONECARATに相談してみてください!
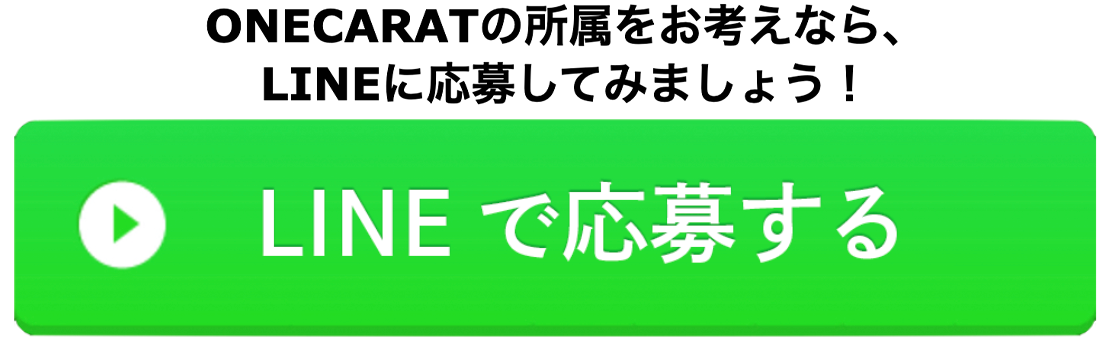 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
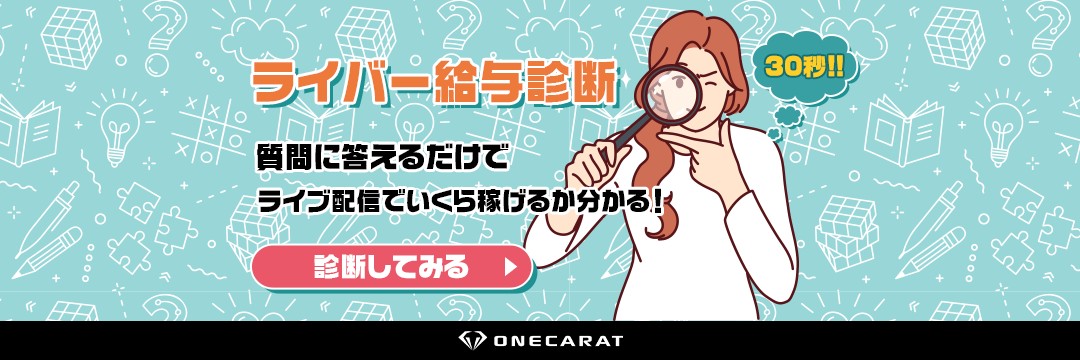
30秒で診断!ライバー給与診断!
アクセスランキングアクセスランキングアクセスランキング
すべて
Pococha
17LIVE
BIGO LIVE
TikTokLIVE
イベント
インタビュー
ユーザーから受けた通報は1件づつ確認しているため、全ての通報を迅速に確認し対応することが難しいため。
また通報を受けたというだけで、対象のユーザーを違反と断定し取り締まることはできません。
【対応策】
①不正と思われる行動があるユーザーの検知精密化
②ユーザーからの通報に対する調査手順の効率化
③より効率的に違反行動を検知するための通報システムの構築
などを行うことで対応速度を速め精度を上げる取り組みをしていく予定です。